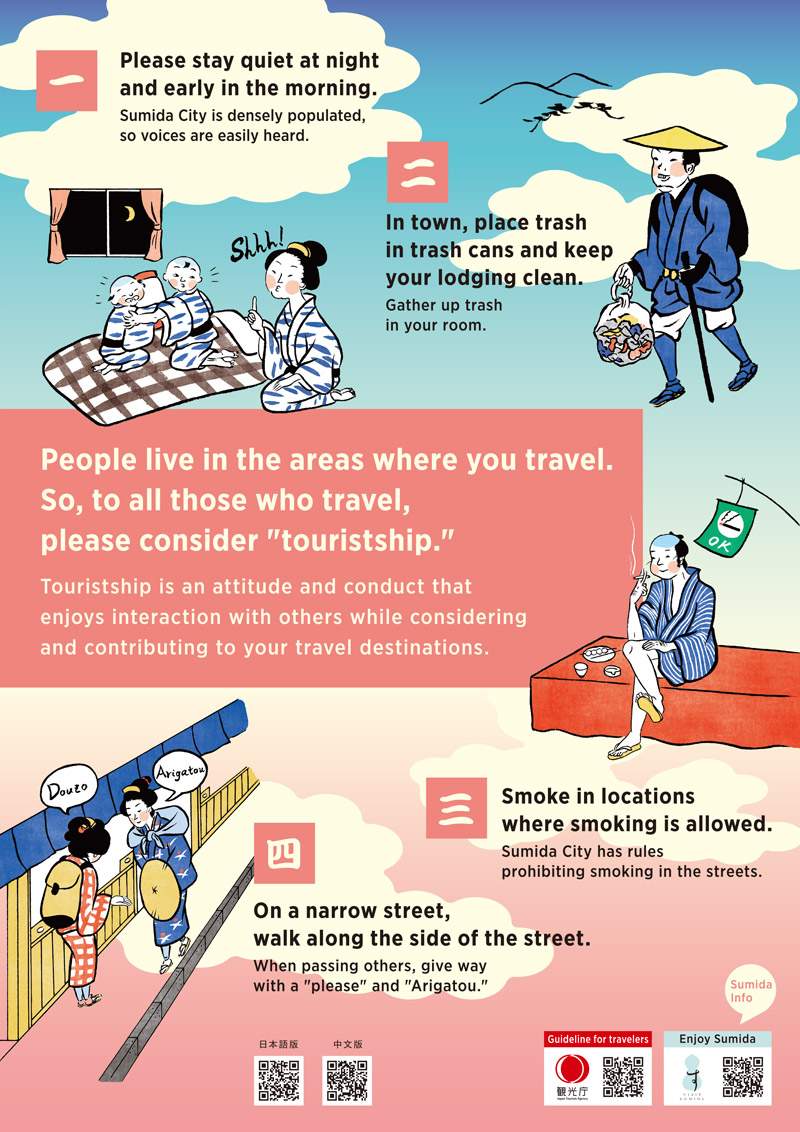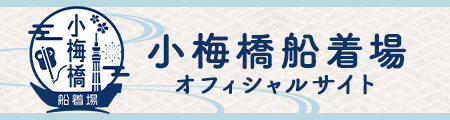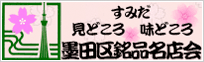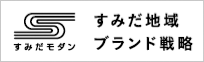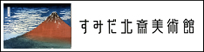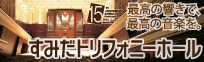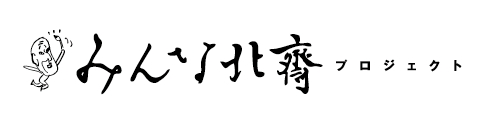討入りの舞台 吉良邸周辺を訪ねる忠臣蔵
忠臣蔵 討入りの舞台吉良邸周辺を訪ねる
両国には吉良邸をはじめ忠臣蔵の舞台となったスポットがたくさんあります。
忠臣蔵ゆかりの地を辿りながら、歴史に触れてみてはいかがですか?時代劇ファンにはお勧めのコースです!
コース詳細
両国観光案内所

両国エリアを中心した観光案内やパンフレットが設置されています。両国観光案内所発のガイドつきツアーも開催(夏季・冬季除く)しています。すみだのお土産も販売しています。
回向院

明暦3年(1657年)の「明暦の大火」で亡くなった方を鎮魂するために建立された両国のシンボル的寺院です。討入り後の赤穂義士はここで休息をとろうとしましたが、開門時刻の前だったため入れず、両国橋まで歩きました。
大高源五の句碑

討入り当日、赤穂義士のひとり、大高源五の知人が、吉良邸の近くで年忘れ句会を開いていた。その会で知人が句を詠むと、目的を遂げた大高源五がその場で返句したといわれています。
旧両国橋・広小路跡

討入り後、赤穂義士が休息をした場所です。劇作では両国橋を渡ったことになっています。しかし実際は、赤穂義士は登城する大名や旗本の行列を避け、一之橋、永代橋を経由して泉岳寺を目指しました。
一之橋

万治2年(1659年)に堅川の工事の際に架けられました。赤穂義士が泉岳寺に引き揚げる際に、最初に渡った橋として知られています。隅田川に一番近いので「一之橋」という名が付きました。
前原伊助宅跡

"赤穂四十七士の1人、前原伊助が米屋に扮して潜伏していた場所です。吉良邸の裏門とは眼と鼻の先にありました。討入り当日は赤穂義士たちの集合場所になりました。
※赤穂義士は47人いたため、赤穂四十七士と呼ばれています。
吉良邸正門跡

吉良邸の正門があった場所です。元禄15年(1702年)12月14日、大石内蔵助以下23名が正門から邸内へ侵入しました。100人以上と装うため、大声をあげながら攻め入ったといわれています。
本所松坂町公園・吉良邸跡

まさにここが討入りの舞台となった地です。正面右には「赤穂浪士遺蹟 吉良邸跡」の石碑があります。園内には、愛知県西尾市の華蔵寺にある上野介座像を再現したものがあります。
本所松坂町の石碑

「松坂町」は、昭和4年(1929年)の区画整理で無くなりましたが、その町名が消えてしまうのを惜しみ、建てられた石碑です。