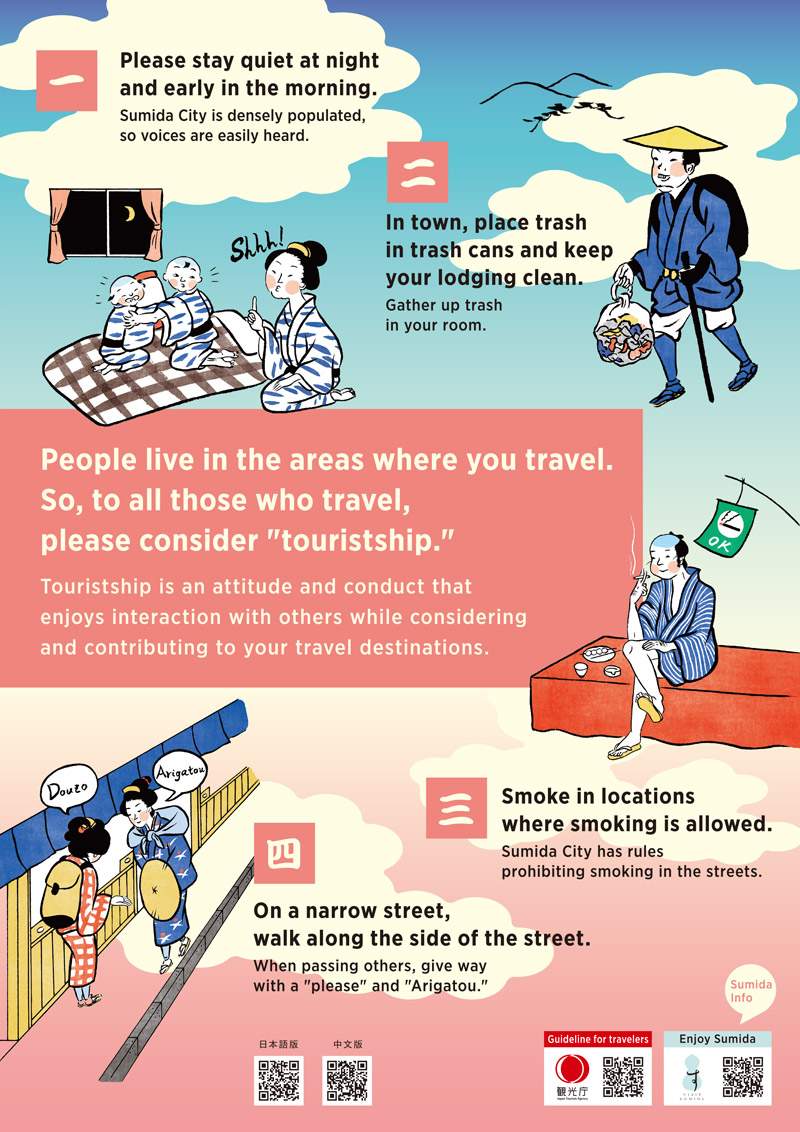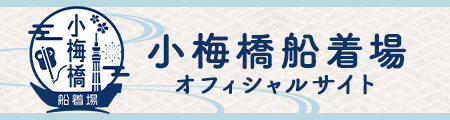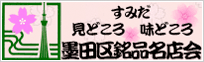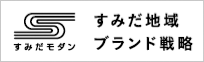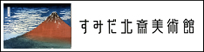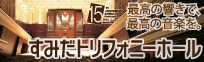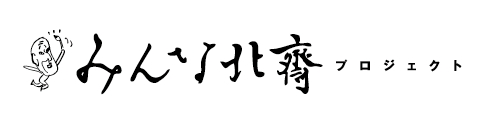歴史と伝説の幻の道を歩く鎌倉街道下ノ道
鎌倉街道下ノ道 歴史と伝説の幻の道を歩く
鎌倉時代(1185-1333年)、当時の幕府があった鎌倉と各地方を結ぶ道を「鎌倉街道」といいました。
すみだを通っていたのは「下ノ道」といいました。この道に立つと「いざ 鎌倉(いざ かまくら)」と声が聞こえてくるようです。
コース詳細
鎌倉街道下ノ道 説明板

鎌倉と下総・上総(現在の千葉県)を結ぶ道は、古くから鎌倉街道 下ノ道と呼ばれていました。源頼朝が常陸国や奥州の征伐の際に通ったといわれています。郷土の歴史を知る上では欠かせない道すじです。
隅田川神社

亀に乗った水神が浮州に上陸し、隅田川の総鎮守の神になったとされています。水神社(すいじんじゃ)とも呼ばれ、狛犬ならぬ狛亀が左右に鎮座しています。
木母寺

謡曲「隅田川」として歌舞伎や能の演目にもなっている「梅若伝説」ゆかりのお寺です。平安時代(794-1185年)、京都から人買いに連れ去られ、隅田川のほとりで12歳で亡くなった梅若丸と、我が子を探し歩きその死を知る母の物語です。その母子を供養したお寺が梅若寺であり、現在の木母寺です。
正福寺

東向島にある蓮花寺の末寺です。参道には、東京都内最古のものといわれる板碑がたてられています。これには宝治2年(1248年)年の銘があり、付近の御前栽畑から出土したと伝えられています。
圓徳寺

朱色の山門が目立つ曹洞宗の寺院です。境内には文化8年(1811年)の銘がある「宝篋印塔(ほうきょいんとう)」や、三猿の台座に乗った阿弥陀立像の庚申塔などが残されています。
多聞寺

墨田区最北端のお寺。茅葺きの山門など多くの文化財が大震災と戦災での消失を免れ残っています。「たぬき寺」とも呼ばれ広く親しまれています。